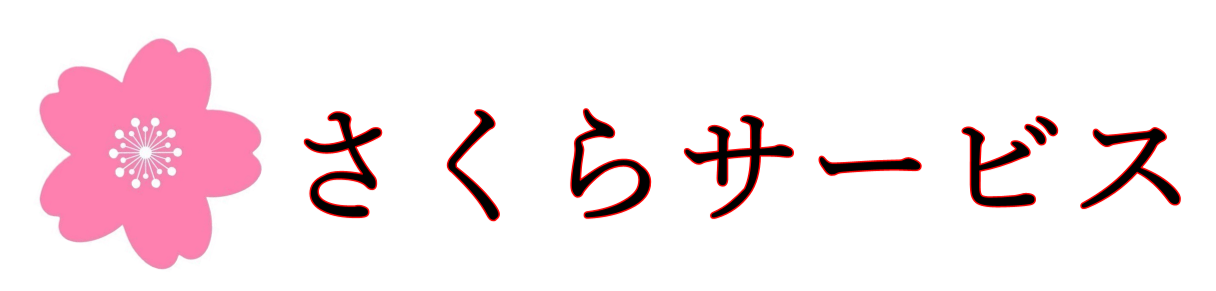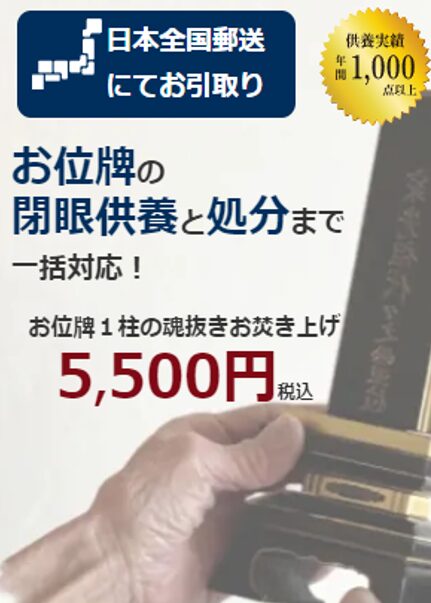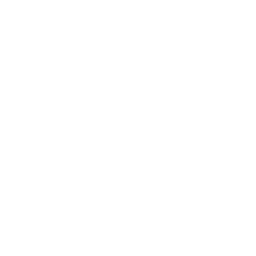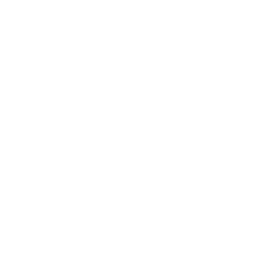「位牌」の作り方、文字の書き方、ルールについて
家族や親族が亡くなった時には故人の魂を宿す位牌という礼拝の対象を作ります。そこに書くべき内容や文字の入れ方などのルールいついて説明します。

1.位牌に書かれた文字の意味
位牌とは故人の霊を祀るために作りますが、お寺のお坊さんに頂いた新しい名前である戒名や法名などを書き入れます。故人の生前の名前やそれに由来するような文字が含められています。
1-1.梵字
お寺から戒名と白木位牌を頂いた際、戒名の上に小さな記号のような文字がついているケースがありますが、こちらの文字は梵字(ぼんじ)と呼ばれる文字になります。
梵字にはその文字自体に神様が宿っているとされ、その一文字で神仏を表すといわれていました。お位牌も同じく、お位牌にある梵字は日本の仏様を意味する文字となっています。お位牌に梵字をつけることで、戒名を授かった故人の方が仏様の弟子となることを表します。
1-2.戒名(法名)
戒名は、仏様の弟子に授けられる名前という意味もあります。現在では亡くなってから戒名をつけてもらうというのは一般的になっていますが、仏教徒としての生活を送る場合には、生きている間に戒名を授けてもらうこともあります。
仏弟子として授かる名前を浄土真宗は戒名とは言わず法名といい、日蓮宗では法号と言います。
1-3.俗名
俗名とは、生前に名乗っていた姓名のことを言い、戒名に対して使われることが多いです。
本来の意味は仏門に入る前の名前を指しますが、一般的には亡くなってから戒名を授けられるので、通用の俗名の意味は、亡くなる前に使っていた名前を指します。そして戒名がある時には位牌の裏に、戒名をつけない場合には位牌の表に記します。
2.位牌の文字のレイアウトや書き方のルール
位牌のレイアウトや書き方などにはルールがあります。具体的な文字の内容やレイアウトなどはそれぞれの宗派によって異なりますから、故人の宗派を確認することが大切です。
初めて位牌と作るという場合にはその位牌が、今後位牌や仏壇を継いでいく次の世代のベースになりますから、慎重に内容やレイアウトなどについて考える必要があります。とはいえ、現代ではほとんどの場合は仏具屋さんや位牌の製造業者に任せれば、最適なレイアウトと形で出来上がってきます。
2-1.1人の位牌を作る場合
故人1人の位牌を作る場合、表面の中央に、戒名を入れます。
梵字については寺院から戒名をいただいた際に入っているようであれば付けます。
表面に没年月日を配置する場合は、バランスよく仏具店等が配置して印字してくれます。
裏面には俗名と亡くなった時の年齢を書き記すのが一般的ですが、没年月日を裏に入れるケースもあります。宗派によっては梵字を入れるケースと入れないケースがありますので、その宗派のしきたりに従いましょう。
真言宗の場合には、基本的には同じレイアウトになりますが、戒名の下の「位」という置字を入れることになります。
2-2. 夫婦の位牌を作る場合
夫婦の場合には、ひとつの位牌に夫婦の戒名を入れることが可能になっています。
表書きには、夫の戒名と妻の戒名、没年月日を記入します。夫が右で妻が左というのが一般的です。
裏には、夫と妻の俗名、亡くなった年齢を入れましょう。こちらも、夫の俗名を右側に、妻を左側にというのが基本です。1人の位牌を作る時と同じで、真言宗の場合には戒名の下に「位」を書き記します。梵字についても同じで、宗派のしきたりに従います。
2-3.先祖代々の位牌を作る場合
先祖代々の位牌を作る場合には表書きに「○○家先祖代々之霊位」と記入します。
曾祖父や祖父母と先祖代々の位牌すべてを仏壇に飾るということはスペース的にも難しく、先祖代々の位牌をひとつにまとめて供養するというのが一般的です。裏書きはなにも記入しません。
梵字や冠文字については今までの位牌を参考にするといいでしょう。また、先祖代々の位牌を作る際には、家紋を入れるというケースもあります。
3. 仮の位牌の処分の方法
位牌は通常四十九日までに作ります。それまでの間に仮で使う白木の位牌は入れ替えで処分することになります。

流れとしては位牌(本位牌)が完成したら四十九日の法要の際にお坊さんが開眼供養を行い魂を新しい位牌(本位牌)入れてくれます。そして不要になった仮の位牌(白木位牌)は魂が宿っていないのでお焚き上げという供養をして処分するというのが一般的です。
お焚き上げの方法は、通常なら四十九日の法要が終わったらお坊さんがそのまま持って帰って寺で焼いてくれるか、仏具屋さんが引き取ってくれて、指定のお寺でお焚き上げしてくれます。。
ところが最近ではお寺の境内でお焚き上げできるところが少なくなって、迷惑条例や消防法の関係で、盛大に燃やして供養するようなイベントが出来るところはかなり田舎のお寺でないと難しくなっています。

そんなこともあってお寺も仏具屋さんも白木位牌を持って帰らずそのまま家に残されることが増えてきました。
白木位牌の処分に困ったら、お焚き上げの専門業者がいますので相談してみてください。
お位牌の郵送受付供養サービス さくらサービス東京のご案内はコチラ